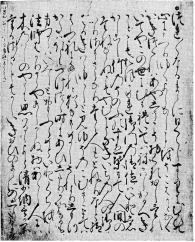徒然草

第1~50段
つれづれなるままに(序段)/ いでや、この世に生まれては(第1段)/ いにしへの聖の御代(第2段)/ よろづにいみじくとも(第3段)/ あだし野の露消ゆる時なく(第7段)/ 世の人の心惑はすこと(第8段)/ 女は髪のめでたからんこそ(第9段)/ 家居のつきづきしく(第10段)/ 神無月の頃(第11段)/ 折節の移りかはるこそ(第19段)/ 雪のおもしろう降りたりし朝(第31段)/ 九月廿日の頃(第32段)/ 手のわろき人の(第35段)/ 朝夕隔てなく馴れたる人の(第37段)/ 五月五日、賀茂の競べ馬を(第41段)/ 公世の二位のせうとに(第45段)
第51~100段
亀山殿の御池に(第51段)/ 仁和寺のある法師(第52段)/ これも仁和寺の法師(第53段)/ 家の作りやうは(第55段)/ 道心あらば(第58段)/ 大事を思ひたたん人は(第59段)/ 筑紫になにがしの押領使(第68段)/ 名を聞くよりやがて(第71段)/ 蟻のごとくに集まりて(第74段)/ 何事も入り立たぬ(第79段)/ 竹林院入道左大臣殿(第83段)/人の心すなほならねば(第85段)/ 或者、小野道風の書ける(第88段)/ 奥山に猫またといふもの(第89段)/ 大納言法印の召し使ひし(第90段)/ 或人、弓射る事を習ふに(第92段)/ 堀河相国は(第99段)
第101~150段
尹大納言光忠入道(第102段)/ 女のもの言ひ掛けたる(第107段)/ 寸陰惜しむ人なし(第108段)/ 高名の木のぼり(第109段)/ 双六の上手(第110段)/ 四十にもあまりぬる人の(第113段)/ 寺院の号(第116段)/ 友とするにわろき者(第117段)/ 唐の物は(第120段)/ 養ひ飼ふものには(第121段)/ 人の才能は(第122段)/ 顔回は(第129段)/ 貧しき者は(第131段)/ 花はさかりに(第137段)/ 身死して財残ることは(第140段)/ 悲田院堯蓮上人は(第141段)/ 心なしと見ゆる者(第142段)/ 能をつかんとする人(第150段)
第151~200段
ある人のいはく(第151段)/ 西大寺静然上人(第152段)/ 為兼大納言入道召し捕られて(第153段)/ この人、東寺の門に(第154段)/ 世に従はむ人は(第155段)/ 人間の営みあへるわざ(第166段)/ 一道に携はる人(第167段)/ 年老いたる人の(第168段)/ さしたることなくて(第170段)/ 貝を覆ふ人の(第171段)/ 若き時は(第172段)/ 相模守時頼の母は(第184段)/ ある者、子を法師に(第188段)/ 今日は、その事をなさんと思へど(第189段)/ 妻といふものこそ(第190段)/ 夜に入りて(第191段)
第201~243段
十月を神無月と言ひて(第202段)/ 徳大寺故大臣殿(第206段)/ 亀山殿建てられんとて(第207段)/ 人の田を論ずるもの(第209段)/ 喚子鳥は(第210段)/ よろづの事は頼むべからず(第211段)/ 平宣時朝臣、老いののち(第215段)/ ある大福長者(第217段)/ よき細工は(第229段)/ 万の咎あらじと思はば(第233段)/ 主ある家には(第235段)/ 丹波に出雲と云ふ所あり(第236段)/ 八つになりし年(第243段)
つれづれなるままに~序段
つれづれなるままに、日暮らし、硯(すずり)に向かひて、心にうつりゆく由(よし)なしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそもの狂(ぐる)ほしけれ。
【現代語訳】
ひとり居で手持ちぶさたなのにまかせて、一日中、硯を前にして、心に映っては消え、映っては消えるつまらないことを、とりとめもなく書きつけると、妙におかしな心地になってくる。
↑ ページの先頭へ
いでや、この世に生まれては~第一段
(一)
いでや、この世に生まれては、願はしかるべき事(こと)こそ多かめれ。
御門(みかど)の御位(みくらゐ)は、いともかしこし。竹の園生(そのふ)の末葉(すゑば)まで、人間の種(たね)ならぬぞ、やんごとなき。一の人の御有様(みありさま)はさらなり、ただ人(うど)も、舎人(とねり)など賜(たま)はる際(きは)は、ゆゆしと見ゆ。その子、孫(むまご)までは、はふれにたれど、なほなまめかし。それより下(しも)つかたは、ほどにつけつつ、時にあひ、したり顔なるも、みづからはいみじと思ふらめど、いとくちをし。
法師(ほふし)ばかり羨(うらや)ましからぬものはあらじ。「人には木の端(はし)のやうに思はるるよ」と清少納言が書けるも、げにさることぞかし。勢ひ猛(まう)にののしりたるにつけて、いみじとは見えず、僧賀聖(ぞうがひじり)の言ひけんやうに、名聞(みやうもん)苦しく、仏の御教(みをし)へに違(たが)ふらんとぞ覚ゆる。ひたふるの世捨て人は、なかなかあらまほしきかたもありなん。
【現代語訳】
いったい、この世に生まれたからは、誰しも願わしいことが多かろう。(中でもいちばん願うのは、富と権力であろう。)
かといって帝の御位はたいそう恐れ多い。帝をはじめ子々孫々に至るまで、皇室の人々は人間界でなく神の子孫であることが尊い。摂政・関白も言うまでもない。それより下の普通の貴族でも、帝から舎人などを賜るほどの身分の方は立派に感じる。そういう人たちの子、孫くらいまでは、たとえ落ちぶれても、なお品位がある。だが、それより下になると、階級に応じてたまたま時勢に乗って得意顔をしているのは、本人は偉くなったつもりだが、はたから見れば実につまらないものだ。
法師ほど、羨ましくないものはない。「世間には木の端のように思われることよ」と清少納言が(『枕草子』に)書いたのも、なるほどもっともである。権勢が盛んで名声が轟くのを聞いても、少しもすごいとは思えず、僧賀上人が言ったように、名声を得るのは僧侶として心苦しく、仏の教えに背いているとしか思えない。ひたすら俗世間と離れて隠棲している世捨て人は、かえって理想にかなっているといえる。
(注)僧賀聖・・・917~1003年。天台宗の僧で、名利を忌み多武峰に隠棲した。
(二)
人は、かたち、ありさまの優れたらんこそ、あらまほしかるべけれ。物うち言ひたる、聞きにくからず、愛敬(あいぎやう)ありて言葉多からぬこそ、飽かず向はまほしけれ。めでたしと見る人の、心劣りせらるる本性(ほんじやう)見えんこそ、口惜しかるべけれ。品(しな)、かたちこそ生まれつきたらめ、心はなどか賢きより賢きにも移さば移らざらん。かたち、心ざまよき人も、才(ざえ)なくなりぬれば、品(しな)くだり、顔憎さげなる人にも立ち交じりて、かけずけおさるるこそ、本意(ほい)なきわざなれ。
ありたきことは、まことしき文(ふみ)の道、作文(さくもん)、和歌、管絃の道、また有職(いうそく)に公事(くじ)の方、人の鏡ならんこそいみじかるべけれ。手などつたなからず走り書き、声をかしくて拍子(ひやうし)とり、いたましうするものから、下戸(げこ)ならぬこそ男(をのこ)はよけれ。
【現代語訳】
人は誰しも、容貌・姿が美しいのが望ましいに決まっているが、話しぶりが聞きやすく、感じがよく魅力的で、余計なことを言わない人こそ、いつまでも向き合っていたいものだ。ただ、立派だと思っていた人が、予想に反して軽蔑せずにいられないような本性を見せるのは、まったく残念なことだ。家柄や容貌こそ生まれつきだが、知性は努力によっていくらでも賢明になっていくものだ。容貌や心ばえがよい人でも、学才を磨かなければ、品位は下がり、下品な顔立ちの人の間に立ち混じって、小さく駄目になってしまう。不本意なことだ。
望ましいのは、四書五経などに通じ、漢詩・和歌を作り、管弦の才能を身につけることである。さらに、宮中の規則や慣例に通じ、人の鏡となれば大したものであろう。文字なども拙くはない程度にすらすらと書き、宴席では美声で一座の音頭を取り、酒は遠慮するものの、まったく飲めない下戸というわけではないのが、男として好ましい。
(注)作文・・・漢詩を作ること。
↑ ページの先頭へ
いにしへの聖の御代の~第二段
いにしへの聖(ひじり)の御世(みよ)の政をも忘れ、民の愁(うれ)へ、国のそこなはるるをも知らず、よろづにきよらを尽くしていみじと思ひ、所せきさましたる人こそ、うたて、思ふところなく見ゆれ。
「衣冠(いくわん)より馬・車にいたるまで、有るにしたがひて用ゐよ。美麗を求むる事なかれ」とぞ、九条殿の遺誡(ゆいかい)にも侍る。順徳院の、禁中の事ども書かせ給へるにも、「おほやけの奉り物は、おろそかなるをもてよしとす」とこそ侍れ。
【現代語訳】
昔の聖帝の御世の政治を忘れ、民の愁い、国力が衰退していくことをも知らず、あらゆることに華美を尽くして立派だと思い、財宝を所狭しと溜め込んでいる人は、何ともひどく、思慮が欠けると見える。
「衣冠から馬・車に至るまで、ありあわせのものを使え。贅沢を求めてはならぬ」と九条殿が子孫に訓戒した書の中にもある。順徳院が宮中のしきたりをお書かせになった書物にも「天皇・皇族のお召し物は、質素なのがよい」とある。
(注)九条殿・・・藤原師輔(908~960年)。正二位右大臣。
↑ ページの先頭へ
よろづにいみじくとも~第三段
よろづにいみじくとも、色(いろ)好まざらん男は、いとさうざうしく、玉の巵(さかづき)の当(そこ)なき心地ぞすべき。露霜(つゆじも)にしほたれて、所(ところ)定めずまどひ歩(あり)き、親のいさめ、世のそしりをつつむに心の暇(いとま)なく、あふさきるさに思ひ乱れ、さるは独り寝がちに、まどろむ夜なきこそをかしけれ。さりとて、ひたすらにたはれたる方にはあらで、女にたやすからず思はれんこそ、あらまほしかるべきわざなれ。
【現代語訳】
万事に優れていても、色恋の情緒を知らない男はたいそう物足りなく、まるで玉製の盃の底が抜けているような感じがする。露や霜に濡れながら、恋人たちを渡り歩き、親の説教や、世間のそしりを憚って神経をすり減らし、あれやこれやと思い乱れ、そのくせ女に逢えず、実際は独り寝の夜が多く、もどろむ夜もないようなのは、何とも味わいがある。そうはいっても、ひたすら色恋に没頭するのではなく、女から安く見られないように行動するのが理想的な身のあり方であろう。
↑ ページの先頭へ
あだし野の露消ゆる時なく~第七段
あだし野の露(つゆ)消(き)ゆる時なく、鳥部山(とりべやま)の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。
命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。かげろふの夕(ゆふべ)を待ち、夏の蝉の春秋(はるあき)を知らぬもあるぞかし。つくづくと一年(ひととせ)を暮らすほどだにも、こよなうのどけしや。あかず惜しと思はば、千年(ちとせ)を過(すぐ)すとも、一夜(ひとよ)の夢の心地こそせめ。住み果てぬ世に、みにくき姿を待ちえて何かはせん。命長ければ恥(はぢ)多し。長くとも四十(よそじ)に足らぬほどにて死なんこそ、めやすかるべけれ。そのほど過ぎぬれば、かたちを恥づる心もなく、人に出で交らはん事を思ひ、夕の陽(ひ)に子孫を愛して、栄(さか)ゆく末を見んまでの命をあらまし、ひたすら世をむさぼる心のみ深く、もののあはれも知らずなりゆくなん、あさましき。
【現代語訳】
あだし野の露が消える時なく、鳥部山の火葬の煙が消えないように、我々の人生が永遠に続くものであるならば、情趣というものはどれほど失せてしまうだろう。人生は限りがあるからこそ価値があるのだ。
命あるものを見れば、人間ほど長生きするものはない。かげろうのように朝生まれて夕方には死に、蝉のように夏だけの命で春や秋を知らない生き物もある。しみじみと一年を過ごすだけでも、この上なくのんびりとした生と言えるではないか。それでも満足できず名残惜しいと思うなら、たとえ千年を過ごしても、一夜の夢のようにはかない心地がするだろう。永遠には生きられないこの世に、老いて醜い姿を晒して、何の甲斐があろうか。長生きをすると恥も多くなる。長くても四十歳に達しないくらいで死ぬのが見苦しくないところだ。そのあたりの年を過ぎてしまうと、老醜を恥じる気持ちもなくなり、人との交わりを欲して、老いさらばえて子や孫を愛し、立身出世する将来を見届けるまでの余命を願い、世に執着する心ばかり深くなり、ついに情趣も分からなくなっていく。情けないことだ。
(注)あだし野・・・京都市右京区嵯峨、小倉山の麓の地。火葬場があり、東山の鳥部山(鳥辺山)と併称された。
↑ ページの先頭へ
世の人の心惑はすこと~第八段
世の人の心惑はすこと、色欲には如(し)かず。人の心は愚かなるものかな。匂ひなどは仮のものなるに、しばらく衣裳に薫物(たきもの)すと知りながら、えならぬ匂ひには、必ず心ときめきするものなり。久米(くめ)の仙人の、物洗ふ女の脛(はぎ)の白きを見て、通(つう)を失ひけんは、まことに手足・はだへなどのきよらに、肥えあぶらづきたらんは、外(ほか)の色ならねば、さもあらんかし。
【現代語訳】
世の人の心を惑わすこととしては、色欲にまさるものはない。人の心は実に愚かである。芳香などは、しょせんかりそめのものなのに、そして一時的に衣裳に薫物をたきしめただけと知っていながら、何ともいえぬよい匂いには、必ず心ときめいてしまうものだ。久米の仙人が、洗濯をしている女の脛の白いのを見て、神通力を失ったというが、たしかに手足・肌などの清らかで、ふっくらと色艶がいいのは、うわべとは違い肉体本来の持つ美しさだから、仙人でさえ神通力を失ったのは、もっともと思われる。
↑ ページの先頭へ
女は髪のめでたからんこそ~第九段
女は髪のめでたからんこそ、人の目立つべかめれ、人のほど、心ばへなどは、もの言ひたるけはひにこそ、ものごしにも知らるれ。ことにふれて、うちあるさまにも人の心を惑はし、すべて女の、うちとけたる寝(い)もねず、身を惜しとも思ひたらず、堪(た)ゆべくもあらぬわざにもよく堪へしのぶは、ただ色を思ふがゆゑなり。
まことに、愛著(あいぢやく)の道、その根深く、源(みなもと)遠し。六塵(ろくぢん)の楽欲(げうよく)多しといへども、みな厭離(えんり)しつべし。その中にただ、かの惑ひのひとつやめがたきのみぞ、老いたるも若きも、智あるも愚かなるも、かはる所なしと見ゆる。
されば、女の髪すぢをよれる綱には、大象(だいぞう)もよくつながれ、女のはける足駄(あしだ)にて作れる笛には、秋の鹿、必ず寄るとぞ言ひ伝へ侍る。自ら戒めて、恐るべく慎むべきは、この惑ひなり。
【現代語訳】
女は、髪が美しいのが、人の目を引くもののようだ。人品や気立てなどは、物を言う様子に現れ、御簾や几帳を隔てていても知ることができる。どうかすると、何でもない仕草でも男の心を惑わし、すべて女が、ぐっすり寝もせず、身を惜しいとも思わず、堪えられないような仕打ちにもよく堪えるのは、ただ男に愛されようと思うがためである。
本当に、愛欲に執着する道の根源は、深く遠い。外の世界には人間の欲望をかきたてるものが多いが、みな避けて遠ざけることができる。しかしその中でただ一つ、愛欲の迷いだけは、老いも若きも、知恵ある者も愚か者も、一切変わるところがないと見える。
だから、女の髪を縒って作った綱には、大きな象もしっかりとつながれるし、女の履いた下駄で作った鹿笛には、秋の牡鹿が必ず寄ってくると言い伝えられている。自ら戒め、恐れ慎むべきは、この愛欲という迷いである。
(注)六塵・・・六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)の感覚器官が認識する「色・声・香・味・触・法」。身を滅ぼすものとして「六つの塵」として列挙される。
(注)楽欲・・・仏教用語で欲望のこと。
↑ ページの先頭へ
家居のつきづきしく~第一〇段
家居(いへゐ)のつきづきしく、あらまほしきこそ、仮の宿りとは思へど、興あるものなれ。
よき人の、のどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も、一際(ひときは)しみじみと見ゆるぞかし。今めかしくきららかならねど、木立ものふりて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに、簀子(すのこ)・透垣(すいがい)のたよりをかしく、うちある調度も昔覚えてやすらかなるこそ、心にくしと見ゆれ。
多くの匠(たくみ)の心を尽してみがきたて、唐(から)の、大和の、めづらしくえならぬ調度ども並べ置き、前栽(せんざい)の草木まで心のままならず作りなせるは、見る目も苦しく、いとわびし。さてもやは、ながらへ住むべき。また時のまの煙ともなりなんとぞ、うち見るより思はるる。大方は家居にこそ、ことざまはおしはからるれ。
後徳大寺大臣(ごとくだいじのおとど)の、寝殿に鳶(とび)ゐさせじとて縄を張られたりけるを、西行が見て、「鳶のゐたらんは、何かは苦しかるべき。この殿の御心(みこころ)さばかりにこそ」とて、その後は参らざりけると聞き侍るに、綾小路宮(あやのこうぢのみや)のおはします小坂殿(おさかどの)の棟(むね)に、いつぞや縄を引かれたりしかば、かの例(ためし)思ひ出でられ侍りしに、「まことや、烏(からす)の群れゐて池の蛙(かへる)をとりければ、御覧じて悲しませ給ひてなん」と人の語りしこそ、さてはいみじくこそと覚えしか。徳大寺にもいかなるゆゑか侍りけん。
【現代語訳】
住居が住む人にふさわしく、あるべき姿であるのは、たとえ現世の仮の宿だとしても、やはり興が深いものだ。
立派な人が、ゆったりと住みなしている所は、差し入る月の色も、ひときわ心に沁みるように見えるものだろう。現代風にきらびやかではないけれど、木立が何となく古色めいて、わざとらしく手を加えない自然な感じの庭の草も風趣ある様子で、簀子や透垣の配置も面白く、何気なく置いてある道具類も古風な感じで落ち着いているのが、奥ゆかしく思われる。
多くの職人が心を尽くして磨き立て、唐様の、和様のと、珍しく立派な道具類を並べ置き、庭の植え込みまで人工的に作ってあるのは、かえって見苦しく、たいそう不愉快である。そんなにしたところで、いつまでも生きて住んでいられようか。また、火事になれば一瞬の間に煙ともなるだろうと、一目見るとそう思われる。大体は、住居によって、住む人の人となりは推し量られるものだ。
後徳大寺左大臣が、寝殿に鳶をとまらせまいとして縄を張られていたのを、西行が見て、「鳶がいたとして、何の不都合があろうか。この殿の御心はそんな程度であったか」といって、その後は参上しなかったと聞いてたので、綾小路宮がお住まいの小坂殿の棟に、いつだったか縄を張られたので、西行のことを思い出しが、ある人が、「烏の群れが池の蛙を取るので、宮さまが御覧になって可哀そうに思われたからなのです」と語ったが、そういうことならばと感心した。徳大寺にも何か理由があったのだろうか。
(注)後徳大寺左大臣・・・藤原実定(1139~1191年)。正二位左大臣。
(注)綾小路宮・・・亀山院皇子の性恵法親王(生没年未詳)。
【PR】
↑ ページの先頭へ
神無月の頃~第一一段
神無月(かみなづき)の頃、栗栖野(くるすの)といふ所を過ぎて、ある山里にたづね入ること侍りしに、遥(はる)かなる苔の細道をふみ分けて、心細く住みなしたる庵(いほり)あり。木の葉に埋(うづ)もるる懸樋(かけひ)の雫(しづく)ならでは、つゆおとなふものなし。閼伽棚(あかだな)に菊、紅葉(もみぢ)など折り散らしたる、さすがに住む人のあればなるべし。かくてもあられけるよとあはれに見るほどに、かなたの庭に、大きなる柑子(かうじ)の木の、枝もたわわになりたるが、周(まは)りを厳(きび)しく囲ひたりしこそ、少しこと冷(さ)めて、この木なからましかばと覚えしか。
【現代語訳】
十月の頃、栗栖野という所を通り過ぎて、ある山里にたずね入ることがあり、はるかに続く苔むした細道を踏み分けて行くと、ひっそりと人が住んでいる草庵があった。木の落葉に埋もれる懸樋から落ちる水のしずくのほかに音を立てるものはない。閼伽棚には菊や紅葉などを折って適当に置いてあるのは、それでも住む人があるからなのだろう。こんな寂しいところでも住むことができるのかと、しみじみ思って見ているうちに、向こうの庭に、大きな蜜柑の木で、枝もたわわに実がなっているのがあり、その周囲を厳重に囲ってあるのは、少し興ざめがして、この木がなければどんなによかったかと思ったことだ。
(注)閼伽棚・・・仏に供える水や花を置くための棚。
↑ ページの先頭へ
折節の移りかはるこそ~第一九段
(一)
折節(をりふし)の移り変るこそ、ものごとにあはれなれ。
「もののあはれは秋こそ勝(まさ)れ」と、人ごとに言ふめれど、それもさるものにて、いま一際(ひときは)心も浮き立つものは、春の気色(けしき)にこそあめれ。鳥の声なども殊(こと)の外(ほか)に春めきて、のどやかなる日影に、垣根の草萌え出(い)づるころより、やや春ふかく霞(かす)み渡りて、花もやうやう気色(けしき)立つほどこそあれ、折しも雨風(あめかぜ)うち続きて、心あわただしく散り過ぎぬ。青葉(あをば)になり行くまで、よろづにただ心をのみぞ悩ます。花橘(はなたちばな)は名にこそ負(お)へれ、なほ、梅の匂ひにぞ、いにしへの事も立ち返り、恋しう思ひ出でらるる。山吹(やまぶき)の清げに、藤のおぼつかなきさましたる、すべて、思ひ捨て難きこと多し。
【現代語訳】
季節の移り変わりというのは、何かにつけて趣のあるものだ。
「しみじみとした情緒は、秋が最も優れる」と、誰もが言うが、たしかにもっともだと思うものの、今一段と心が浮き立つのは、春の光景だろう。鳥の声などもことのほか春めいて、のどかな日の光に、垣根の草が萌え出すころから始まり、次第に春が深まっていき霞が一面にわたって、桜の花もだんだんと咲き出そうとする、ちょうどその折に雨や風が続いて、あわただしく散っていく。その後、青葉になっていくまで、いろいろと気ばかりもんでしまう。橘の花は昔から親しくした人を思い出させる花として有名だが、やはり私は梅の香りによって、昔がよみがえって懐かしく思い出される。山吹が清らかに咲き、藤の花房のぼんやりとしたようす、それらすべてに無関心でいられない。
(二)
「灌仏(くわんぶつ)の頃、祭りの頃、若葉の梢(こずゑ)涼しげに茂りゆくほどこそ、世のあはれも、人の恋しさも増され」と、人の仰せられしこそ、げにさるものなれ。五月(さつき)、菖蒲(あやめ)ふく頃、早苗(さなへ)取る頃、水鶏(くひな)のたたくなど、心細からぬかは。六月(みなづき)の頃、あやしき家に夕顔の白く見えて、蚊遣火(かやりび)ふすぶるもあはれなり。六月祓(みなづきばらへ)またをかし。
七夕(たなばた)祭るこそなまめかしけれ。やうやう夜寒(よさむ)になるほど、雁(かり)鳴きて来るころ、萩(はぎ)の下葉(したば)色づくほど、早稲田(わさだ)刈り干すなど、取り集めたることは秋のみぞ多かる。また野分(のわき)の朝(あした)こそをかしけれ。言ひ続くれば、みな源氏物語、枕草子などに言古(ことふ)りにたれど、同じこと、また今更(いまさら)に言はじとにもあらず。おぼしきこと言はぬは腹ふくるるわざなれば、筆に任せつつ、あぢきなきすさびにて、かつ破(や)り捨(す)つべきものなれば、人の見るべきにもあらず。
【現代語訳】
「四月の灌仏会や賀茂祭の頃の、梢に若葉が涼しそうに茂っていく時分が、世のしみじみした情緒も、思う人への恋しさも一段とまさる」と、ある人がおっしゃったが、本当にその通りだ。五月、菖蒲を家々の軒にさす頃、早苗をとって田植えをする頃、水鶏が戸をたたくように鳴く頃など、物寂しく感じない人があろうか。六月の頃、質素な家の垣根に夕顔の花が白く浮かんで見えたり、蚊遣火が煙っているのも、ひなびた感じで趣深い。夏の終わりを告げる六月祓の行事もまたおもしろい。
秋になって、七夕祭りをするのは優雅だ。しだいに夜の寒さが感じられ、雁が鳴いて渡って来るころ、萩の下葉が色づき、早稲の刈り取って干すなど、いろいろと寄せ集めたような風物が秋にはとくに多い。また、台風が過ぎた翌朝の景色はとても興味深い。こういうことを言い続けていると、みな源氏物語や枕草子などで言い古してしまっているが、同じ事を改めて言っていけなくはなかろう。思っていることを言わないのは腹の張ったような気持ちがして、筆に任せつつ、つまらない慰み書きをし、書くはしから破り捨てるべきものだから、人が見る価値もなかろう。
(三)
さて冬枯(ふゆが)れの気色(けしき)こそ、秋にはをさをさ劣るまじけれ。汀(みぎは)の草に紅葉(もみぢ)の散りとどまりて、霜(しも)いと白う置ける朝(あした)、遣水(やりみづ)より煙(けぶり)の立つこそをかしけれ。年の暮れ果てて、人ごとに急ぎ合へる頃ぞ、またなくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の寒けく澄める廿日(はつか)余りの空こそ、心細きものなれ。御仏名(おぶつみやう)・荷前(のさき)の使(つかひ)立つなどぞ、あはれにやんごとなき。公事(くじ)ども繁(しげ)く、春の急ぎに取り重ねて催(もよほ)し行はるるさまぞ、いみじきや。追儺(ついな)より四方拝(しはうはい)に続くこそ、面白けれ。晦日(つごもり)の夜、いたう暗きに、松どもともして、夜半(よは)過ぐるまで、人の門(かど)たたき走り歩(あり)きて、何事にかあらん、ことごとしくののしりて足を空に惑(まど)ふが、暁(あかつき)がたより、さすがに音なくなりぬるこそ、年の名残(なごり)も心細けれ。亡き人の来る夜とて、魂(たま)祭るわざは、このごろ都にはなきを、東(あづま)の方(かた)には、なほする事にてありしこそ、あはれなりしか。
かくて明けゆく空の気色(けしき)、昨日に変りたりとは見えねど、引き換へ珍しき心地ぞする。大路(おほち)のさま、松立て渡して、華やかにうれしげなるこそ、またあはれなれ。
【現代語訳】
さて冬枯れの景色は、これも秋に少しも劣らないだろう。池の水際の草に紅葉が散り留まり、それに霜が白々と降りている朝、遣水からぼんやり水蒸気が立ち上っているのは趣がある。年が押し迫って、人がみな忙しそうにしている頃はまたとなく趣がある。殺風景だといって見る人もいない月が、寒々と澄んでいる二十日過ぎの空こそ、人から忘れられた心細さを感じる。宮中では、御仏名があり、荷前の使いが出発するなど、しみじみと尊い。ほかにも諸儀式が続き、それが新春の準備と重なって催されるさまは、実にすばらしい。大晦日の追儺から元旦の四方拝へと続くのがおもしろい。庶民については、大晦日の夜、真っ暗闇の中を、松明を灯して、夜中過ぎまで家々の門をたたいて走り回り、何事かと思うほど大げさに騒いで、足も宙を浮くように慌てふためいていた連中が、明け方にはさすがに静かになると、行く年の名残が感じられて心細いものだ。大晦日は死んだ人の魂が帰ってくる夜だとして魂祭をする習慣は、この頃は京都では行われないが、東国ではまだ行われているというのは感慨深かった。
こうして夜が明けていく新年の空のようすは、別に昨日と変わったようには見えないが、やはりどこか違って清新な気持ちがするものだ。大路のようすも、門松を立て並べて、はなやかで嬉しそうであるのは、またしみじみと趣がある。
(注)荷前・・・諸国が毎年貢ずる初穂。神宮や諸陵に奉る使いが遣わされる。
(注)追儺・・・大晦日に宮中で行われる、鬼払いの儀式。
(注)四方拝・・・元日に天皇が清涼殿東庭で天地や山陵を配する儀礼。
【PR】
↑ ページの先頭へ
雪のおもしろう降りたりし朝~第三一段
雪のおもしろう降りたりし朝(あした)、人のがり言ふべきことありて、文(ふみ)をやるとて、雪のこと何とも言はざりし返事(かへりごと)に、「この雪いかが見ると、一筆(ひとふで)載せ給はぬほどの、ひがひがしからん人の仰せらるること、聞き入るべきかは。かへすがへす口惜しき御心なり」と言ひたりしこそ、をかしかりしか。
今は亡き人なれば、かばかりの事も忘れがたし。
【現代語訳】
雪が趣深く降っていた朝、ある人に言わなければならないことがあって手紙をやろうと、用件だけ書いて雪のことは何も書かなかった、その返事に、「この雪をどう御覧ですかと一筆お書き添えにならぬほどの、無風流なひねくれた人の頼み事は聞き入れることなどできない、全くもって情けない」と書かれていたのが、面白かった。
その人は今は亡き人なので、この程度のちょっとした事も忘れられない。
↑ ページの先頭へ
九月廿日の頃~第三二段
九月廿日(ながつきはつか)の頃、ある人に誘はれ奉(たてまつ)りて、明くるまで月見歩くこと侍りしに、思(おぼ)し出(い)づる所ありて、案内(あない)させて入(い)り給ひぬ。荒れたる庭の露(つゆ)しげきに、わざとならぬ匂ひ、しめやかにうち薫(かを)りて、忍びたる気配(けはひ)、いとものあはれなり。
よきほどにて出で給ひぬれど、なほ事(こと)ざまの優(いう)に覚えて、物の隠れよりしばし見ゐたるに、妻戸(つまど)を今少し押し開けて、月見る気色なり。やがて、掛けこもらましかば、口惜しからまし。跡まで見る人ありとは、いかでか知らん。かやうのことは、ただ朝夕の心づかひによるべし。その人、ほどなく失(う)せにけりと聞き侍りし。
【現代語訳】
九月二十日の頃、ある方にお誘いいただいて、夜明けまで月見をして歩き回ることがあった。途中、その方がふと思い出された所があり、従者に取り次ぎさせ、その家の中にお入りになった。私は外でその家のようすを見ていると、荒れた庭には露がたくさん降りていて、わざわざ焚いたのではない香の匂いが、しんみりと薫って、ひっそり暮らしているようすが、とても趣深く感じた。
ほどよい時間にその方が出てこられたが、なおその家のようすが優雅に感じられ、物陰からしばらく見ていると、その家のご婦人が、その方が出てこられた妻戸を少しばかり押し開けて、月を眺めるようすだ。もしこれが客を送り出した後、すぐに掛け金をかけて引きこもってしまっては、情緒もなく残念だったろう。後まで見ている人があるとは知るはずもない。このような自然で優雅なふるまいは、ただ朝夕の心がけによるのだろう。その人は、まもなく亡くなったとお聞きした。
(注)妻戸・・・左右両側に開く戸。
↑ ページの先頭へ
手のわろき人の~第三五段
手のわろき人の、はばからず文(ふみ)書き散らすは、よし。見苦しとて、人に書かするは、うるさし。
【現代語訳】
字の上手でない人が、遠慮しないで無造作に手紙を書くのは、いいことだ。筆跡が見苦しいからといって、他人に代筆させるのは、いやみなものだ。
(注)手・・・文字、筆跡のこと。
↑ ページの先頭へ
朝夕隔てなく馴れたる人の~第三七段
朝夕、隔てなく馴(な)れたる人の、ともある時、我に心おき、ひきつくろへるさまに見ゆるこそ、「今更、かくやは」など言ふ人もありぬべけれど、なほ、げにげにしく、よき人かなとぞ覚ゆる。
疎(うと)き人の、うちとけたる事など言ひたる、又よしと思ひつきぬべし。
【現代語訳】
朝夕隔てなく馴れ親しんだ人が、何かの時に、こちらに気を使って、改まった様子をするのを見て、「今更そんなことをする仲でもないのに」など言う人もあるだろうが、やはり誠実な感じがして、いい人だなと思われる。
一方、疎遠になっていた人が、うちとけた事など言ってくるのも、気が利いていてよい感じがする。
【PR】
↑ ページの先頭へ
五月五日、賀茂の競べ馬を~第四一段
五月(さつき)五日、賀茂(かも)の競馬(くらべうま)を見侍りしに、車の前に雑人(ざふにん)立ち隔てて見えざりしかば、おのおの下りて、埒(らち)の際(きは)に寄りたれど、殊(こと)に人多く立ち混みて、分け入りぬべきやうもなし。
かかる折に、向ひなる楝(あふち)の木に、法師の登りて木の股(また)についゐて物見るあり。取り付きながら、いたう睡(ねぶ)りて、落ちぬべき時に目を醒(さ)ますこと、度々なり。これを見る人、あざけりあさみて、「世のしれ者かな。かく危(あやふ)き枝の上にて、安き心ありて睡(ねぶ)るらんよ」と言ふに、我が心にふと思ひしままに、「我らが生死(しやうじ)の到来、ただ今にもやあらん。それを忘れて物見て日を暮(くら)す、愚かなることは、なほ勝(まさ)りたるものを」と言ひたれば、前なる人ども、「誠にさにこそ候(さうら)ひけれ。もっとも愚かに候ふ」と言ひて、みな後(うしろ)を見返りて、「ここに入らせ給へ」とて、所を去りて、呼び入れ侍りにき。
かほどの理(ことわり)、誰(たれ)かは思ひよらざらんなれども、折からの思ひかけぬ心地して、胸に当たりけるにや。人、木石(ぼくせき)にあらねば、時にとりて、物に感ずることなきにあらず。
【現代語訳】
五月五日、賀茂神社の競馬を見物したが、乗ってきた牛車の前に群集が立ちふさがって見えず、それぞれが車から降りて馬場の柵の際に近寄ったものの、そこは特に混雑していて分け入ることができそうにない。
そうした時に、向こう側の楝の木に法師が登り、木の股にひょいと腰掛けて見物しているではないか。彼は木にとりついたまま眠りこけて、今にも落ちそうになっては目を覚ますのをたびたび繰り返していた。これを見た人たちは、あざけりあきれて、「天下の大馬鹿者だよ。あんな危ない枝の上で、よくものんびりと眠っていられるものだ」と言ったので、私は心にふと思ったままに、「我々に死がやってくるのも、たった今かもしれない、それを忘れて見物をして一日を暮らしている、その愚かさはあの法師よりなおひどいのに」と言ったところ、前にいた人々が、「まことにその通りです。全く愚かなことです」と言って、みんな後ろを振り返って、「ここにお入りなさい」と、場所を空けて私を呼び入れてくれた。
この程度の道理は、誰だって思いつかないことではないが、ちょうど時機よく思いがけない気持ちがして胸に響いたのだろうか。人は木石ではないので、時によってものを深く感ずることがないわけではないようだ。
↑ ページの先頭へ
公世の二位のせうとに~第四五段
公世(きんよ)の二位のせうとに、良覚僧正(りやうがくそうじやう)と聞こえしは、極めて腹悪しき人なりけり。坊の傍らに、大きなる榎(え)の木のありければ、人、「榎木(えのきの)僧正」とぞ言ひける。この名、しかるべからずとて、かの木を伐られにけり。その根のありければ、「切杭(きりくひ)の僧正」と言ひけり。いよいよ腹立ちて、切杭を掘り捨てたりければ、その跡、大きなる堀にてありければ、「掘池(ほりけの)僧正」とぞ言ひける。
【現代語訳】
従二位・藤原公世の兄で、良覚僧正と申し上げた方は、とても怒りっぽい人であった。僧正の住む僧坊のそばに大きな榎の木があったので、人々は「榎の木の僧正」とあだ名した。僧正は、その名はけしからんと言って、その木を切ってしまわれた。しかし、その根が残っていたので、今度は「切りくいの僧正」と呼んだ。ますます腹を立てた僧正は、切り株を掘って捨ててしまったところ、その跡が大きな堀になったので、人々は「堀池の僧正」と呼んだという。
(注)公世の二位・・・藤原公世(?~1301年)。歌人で笙の名手でもあった。
(注)良覚僧正・・・天台宗の大僧正。歌人としても知られる。
↑ ページの先頭へ
(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
「徒然草」について
書名の由来は冒頭の「つれづれなるままに」としるされた序段にあり、「心に映り行くよしなしごと」を書くという前置きに始まり、『枕草子』の形式をかりた243段からなる。しかし、扱われる主題の豊かさと、語り口の柔軟さにおいて際だった特色があり、単なる模倣とはなっていない。
たとえば、倹約をすすめる松下禅尼の教訓的な話(第184段)がある一方で、やることすべてが裏目に出る良覚僧正のユーモラスな話(第45段)などもあり、人生を客観的にみることのできた兼好法師の感覚が、人間の心理、生き方、教養、趣味、実用などにおよぶ多様な話に、統一感をあたえている。全体を貫くのは世の中の移り変わりに対する無常観だが、悲観的な論調に流されず、行間からは人生や自然に対するペーソスが溢れ出ている。また、『平家物語』の作者に関する記述(226段)は現存する最古の物とされる。
『徒然草』が後世にあたえた影響は大きく、成立後しばらくは人の耳目に触れなかったらしいものの、戦乱期を通して知識人に愛読されたほか、江戸時代には広く出版されて、町人層へも浸透した。内容のどの面に中心を置くかにより読み方はさまざまで、教訓書とも、趣味論、人生論などともみなされる。

兼好法師について
兼好が生まれたのは、鎌倉幕府の若き執権・北条時宗が、元軍の襲来を退けた弘安の役(1281年)の2年後。10代後半、堀川家の家司となり、正安3年(1301年)、後二条天皇が即位すると、天皇の母・西華門院が内大臣・堀川具守の子であった縁により、六位の蔵人(天皇の膳の給仕や秘書的役割)として仕える。延慶1年(1308年)、天皇の崩御により宮廷を退く。正和2年(1313年)9月以前に出家。
世捨て人となった理由は不明ながら、政権が交替したことで、兼好の出世に影がさしたことも一因とみられるが、生まれつきの超俗的な性格によるとも推測されている。妻子はなく、70歳余で亡くなった。人生40歳未満が理想だと主張した(第7段)にしては、長命だった。
歌人としては『続千載集』に1首入集し、二条為世門の和歌四天王のひとりに数えられる。康永2/興国4年(1343年)ごろ成立の家集『兼好法師集』は、自選で285首と連歌2句を収める。勅撰集に18首入集している。 主著『徒然草』は「つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて」で始まる序段以下、第1段から第243段まで全244章段からなる随筆集。 私家集に『兼好法師家集』がある。

略年譜
弘安の役
1283年
この年に誕生か。
1284年
北条時宗が死去
1301年
後二条天皇に六位の蔵人として出仕
1307年
従五位に昇叙
この年、関東に下向か
1308年
この年、帰京か
後二条天皇崩御
1312年
この年、関東下向か
1313年
このころまでに出家
『徒然草』の第1部が成立か
1315年
このころ修学院にこもる
1318年
後醍醐天皇が即位
1323年
京の歌壇で活躍
1324年
正中の変
1330年
『徒然草』成立か
1332年
元弘の変に失敗して後醍醐天皇が隠岐に流される
1333年
後醍醐天皇が隠岐を脱出
鎌倉幕府が滅亡
建武の中興
足利尊氏が幕府を開く
後醍醐天皇が吉野に遷幸
1339年
正月、二条為定邸の歌合に出席
後醍醐天皇が吉野で崩御
1345年
『兼好法師家集』成立か
1346年
伊勢参宮
1352年以降
死去(享年70歳余?)。1350年の説もある。
三大随筆の比較
1002年に成立。作者は清少納言。「山は」「川は」などの類聚的な段、自然と人事についての随想的な段、宮仕え中に体験・見聞した日記・自伝的な段などの諸段からなる。自然や人生の美をとらえようとする精神にあふれ、「をかし」の文学と呼ばれる。体言止め・連体形止め・省略などを用いた簡潔な文章で、ほぼ300段からなっている。
方丈記
1212年に成立。作者は鴨長明。前半は、作者の体験した安元の大火・治承の大風、同年の福原遷都・養和から寿永と続いた飢饉・元暦の大地震などの天災地変について記し、後半は自身の閲歴を述べ、続いて草庵での閑寂生活を綴っている。全編を通じて無常観と隠者としての厭世思想が主軸となっている。簡潔な和漢混交文。『枕草子』や『徒然草』のように分段形式はとらず、一貫して流れる筋を一気呵成に展開させている。
徒然草
1330年に成立。作者は兼好法師(吉田兼好)。200数十段からなり、多種多様の随想・見聞を綴っている。有職故実の知識や深い学問教養に基づく趣味論や、無常観に根ざす人生論、また仏教的思想の叙述や過去の回想的記述もある。無常観を基盤に鋭い批判をこめた、さまざまな文体からなっている。
『徒然草の』の各段①
- いでや、この世に生れては
- いにしへのひじりの御代の
- 万にいみじくとも
- 後の世の事
- 不幸に憂に沈める人の
- 前の中書王
- あだし野の露消ゆる時なく
- 世の人の心惑はす事
- 女は、髪のめでたらからんこそ
- 家居のつきづきしく
- 神奈月のころ
- 同じ心ならん人と
- ひとり、燈のもとに文ひろげて
- 和歌こそ、なほをかしきものなれ
- いづくにもあれ
- 神楽こそ、なまめかしく
- 山寺にかきこもりて
- 人は、己れをつづまやかにし
- 折節の移り変るこそ
- 某とかやいひし世捨人の
- 万のことは、月見るにこそ
- 何事も、古き世のみぞ慕はしき
- 衰へたる末の世とはいへど
- 斎宮の、野宮におはしますありさまこそ
- 飛鳥川の淵瀬、常ならぬ世にしあれば
- 風も吹きあへずうつろふ
- 御国譲りの節会行はれて
- 諒闇の年ばかり、あはれなることはあらじ
- 静かに思へば、万に
- 人の亡き跡ばかり、悲しきはなし
- 雪のおもしろう降りたりし朝
- 九月廿日の比、ある人に誘はれたてまつりて
- 今の内裏作り出されて
- 甲香は、ほら貝のやうなるが
- 手のわろき人の
- 久しくおとづれぬ比
- 朝夕、隔てなく馴れたる人の
- 名利に使はれて
- 或人、法然上人に
- 因幡国に、何の入道とかやいふ者の娘
- 五月五日、賀茂の競べ馬を
- 唐橋中将雅清といふ人の子に
- 春の暮つかた
- あやしの竹の編戸のうちより
- 坊の傍に、大きなる榎の木のありければ
- 柳原の辺に
- 或人、清水へ参りけるに
- 光親卿、院の最勝講奉行して
- 老い来りて、始めて道を
- 応長のころ、伊勢国より
- 亀山殿の御池に
- 仁和寺にある法師
- これも仁和寺の法師
- 御室にいみじき児のありけるを
- 家の作りやうは
- 久しく隔たりて逢ひたる人の
- 人の語り出でたる歌物語の
- 道心あらば、住む所にしもよらじ
- 大事を思ひ立たん人は
- 真乗院に、盛親僧都とて
- 御産の時、甑落す事は
- 延政門院、いときなくおはしましける時
- 後七日の阿闍梨
- 車の五緒は、必ず人によらず
- この比の冠は
- 岡本関白殿、盛りなる紅梅の枝に
- 賀茂の岩本橋本は
- 筑紫に、なにがしの押領使など
- 書写の上人は
- 元応の清暑堂の御遊に
- 名を聞くより、やがて
- 賤しげなる物
- 世に語り伝ふる事
- 蟻の如くに集まりて
- つれづれわぶる人は
- 世に覚え花やかなるあたりに
- 世の中に、その比、人のもてあつかひぐさに
- 今様の事どもの珍しきを
- 何事も入りたたぬさましたるぞよき
- 人ごとに、我が身にうとき事をのみぞ
- 屏風、障子などの、絵も文字も
- 羅の表紙は、疾とくく損ずるがわびしきと
- 竹林院入道左大臣殿
- 法顕三蔵の、天竺に渡りて
- 人の心すなほならねば
- 惟継中納言は
- 下部に酒飲まする事は
- 或者、小野道風の書ける
- 奥山に、猫またといふものありて
- 大納言法印の召し使ひし
- 赤舌日といふ事
- 或人、弓射る事を習ふに
- 牛を売る者あり
- 常磐井相国、出仕し給ひけるに
- 箱の作り方に緒を付くる事
- めなもみといふ草あり
- その物に付きて、その物をつひやし損ふ物
- 尊きひじりの言い置きける事を
- 堀河相国は、美男のたのしき人にて
- 久我相国は、殿上にて水を召しけるに
- 或人、任大臣の節会の
- 尹大納言光忠卿、追儺の上卿を
- 大覚寺殿にて、近習の人ども
- 荒れたる宿の、人目なきに
- 北の屋蔭に消え残りたる雪の
- 高野の証空上人、京へ上りけるに
- 女の物言ひかけたる返事
- 寸陰惜しむ人なし
- 高名の木登りといひし男
- 双六の上手といひし人に
- 囲碁、双六好みて明かし暮らす人は
- 明日は遠き国へ赴くべしと
- 四十にも余りぬる人の
- 今出川の大殿、嵯峨へおはしけるに
- 宿河原といふ所にて
- 寺院の号、さらぬ万の物にも
- 友とするに悪き者、七つあり
- 鯉の羹食ひたる日は
- 鎌倉の海に、鰹と言ふ魚は
- 唐の物は、薬の外は
- 養ひ飼ふものには、馬、牛
- 人の才能は、文明らかにして
- 無益のことをなして時を移すを
- 是法法師は、浄土宗に恥ぢずといへども
- 人におくれて、四十九日の仏事に
- ばくちの、負極まりて
- 改めて益なき事は
- 雅房の大納言は、才賢く
- 顔回は、志、人に労を施さじとなり
- 物に争はず
(次頁に続く)